鳳徳小学校でギター&二胡演奏会!
<アウトリーチ活動>第六回を実施しました。
京都市北文化会館は、平成25年度から、芸術家の方々に地域の生活の場へ出向いて活動を行っていただくアウトリーチ活動を開始しました。
夏休みをはさんで、再開二回目です。第六回は二度目の鳳徳小学校の音楽の授業です。ギタリストの加藤信一さんと二胡演奏家の杉原圭子さんに訪問していただきました。
小学5年生約38人の生徒たちは、音楽の教科書の外国の楽器のページに載っている中国の楽器を直に見られるとあって、興味津々です。

最初は加藤さんの演奏で「愛のロマンス」。
「禁じられた遊び」の名前でも知られたスペイン民謡です。
加藤さんがギターについてお話されます。
「ギターはスペイン生まれの楽器ですので、スペイン民謡がよく似合います。小学生の時、父がギターでこの曲を弾いていたのを聴いたのが、私のギターとの出会いで、一遍にギターが大好きになりました。小学生の頃はよくケンカもしましたが、担任の先生が言われた『みんなで協力しあおうね』という言葉は今でも心に残っていて、私の人生に役立っています。音楽は『力をあわせてひとつの曲を作りあげていくよろこび』です。」
ここでアニメーション映画「もののけ姫」から『もののけ姫』をお二人で演奏されます。

杉原さんが中国の楽器についてお話されます。
「みなさん、中国は広い国です。今日はその広さを感じていただけるよう、中国の三つの楽器を持って来ました。本当は、千種類くらいの民族楽器があるんですよ。最初に、アルフーと呼ばれる二胡を演奏します。二胡は中国の江南地方、長江流域の蘇州や杭州あたりの楽器です。主食がお米の地方です。大きな川を小舟がゆっくりと下っていき、やわらかい風が川面をサラサラと揺らす光景を思い描いてみてください。」
曲は「紫竹調」という曲です。

「後のふたつは、ひとつは北の方、もうひとつは南の方の楽器です。今から弾く音楽は北か南か、当ててみてください。特徴をお話ししますと、南の方、広州から香港へかけての地方は、高温多湿で、とにかく働く気がしないんですね。北の方は黄河流域で、乾燥しており、主食が小麦の地方です。」
考える生徒たち。
「これは広東高胡と言って、南の地方の音楽です。ゆったりとした曲ですね。二胡も同じですが、3〜5メートルの大蛇の背中の皮を使っています。」

曲は「平湖秋月」という曲です。
「では北の地方の楽器、高音板胡を弾いてみましょう。」
曲は「三十里舗」という曲です。

「キンキンと大きい音がしますね。桐の板を使っています。黄河流域の特徴は、木がなく、砂漠が迫っていることです。黄土高原から黄砂が日本まで飛んできますね。となりの村まで二日間かかるほど広大な大地です。子供たちは水を汲みに山道を登り降りします。誰もいなくてつまらないから、一人で歌を歌います。誰も聞いていないから、自然に声を張り上げます。そういう地方なんですね。」
「では、二胡を弾いてみたい人はいますか?」
はーい!と一斉に手が挙がります。ジャンケンで二人が前に出て弾きます。

なかなか上手に音を出します。拍手喝采!

「サン=サーンスの「白鳥」を弾きました。フランスの曲でも弾けますよ。日本の楽器は日本の曲しか弾けないことはありません。みなさんも、何にでもチャレンジしてみてください。」

「では最後に、「賽馬」という曲を弾きます。競馬という意味です。草競馬の情景を思い描いてみてください。」
続いて質問コーナー。
「さっきの曲で、馬の声を楽器で弾かれましたが、他の動物の声も弾けますか?」
「鳥の声を弾いてみましょう。」
「これは練習させられるんですよ。鳥が集まって来るまで練習です。」
「弓ははずれないんですか?」
「よく見ていますねェ。そうなんです。ヴァイオリンは弓は別になりますが、中国の楽器は、弓がはずれないんです。失くさなくていいでしょう。」
「馬の頭みたいなのは何ですか?」
「これは龍の頭ですね。螺鈿細工も施されています。みな手作りの美しい楽器ですね。」

「どのような楽譜を使われますか?」
「これもいい質問ですね。中国の楽譜は数字を使ったものです。これは和楽器の楽譜の応用なんですよ。他の楽器と合わす時は五線譜も使います。」
まだまだ質問が尽きない生徒たち。でも終わりの時間が来てしまいました。
夢中になって聴いてくれた生徒たちに、先生方も満足そうです。先生方、本当にありがとうございました。
京都市北文化会館の音楽の授業訪問、秋のシリーズが続きます。引き続き精一杯努めて参りますので、興味をお持ちの方は、どうぞお気軽に京都市北文化会館までお問合せください。
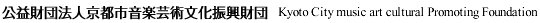
 京都コンサートホール
京都コンサートホール 東部文化会館
東部文化会館 呉竹文化センター
呉竹文化センター 西文化会館ウエスティ
西文化会館ウエスティ 北文化会館
北文化会館 右京ふれあい文化会館
右京ふれあい文化会館 ロームシアター京都
ロームシアター京都 京都市北文化会館
京都市北文化会館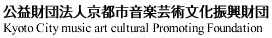
 トピックス/TOPICS
トピックス/TOPICS 施設のご紹介
施設のご紹介 交通アクセス/ACCESS
交通アクセス/ACCESS 自主事業のご案内
自主事業のご案内 パートナーシップ事業
パートナーシップ事業 施設を利用する
施設を利用する 施設の空き情報
施設の空き情報 資料ダウンロード
資料ダウンロード























