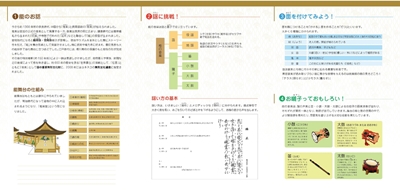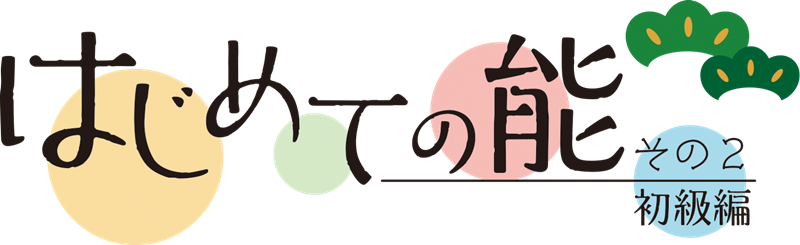 |
謡の響きにドキドキ 小鼓のリズムにワクワク
優雅な舞囃子をじっくり拝見!
2019年1月に開催した『はじめての能 超入門講座』の第2弾は、囃子方(はやしかた=笛や太鼓を演奏する人たち)を迎え、さらに能の魅力をご紹介します。
2月には右京区唯一の能楽堂、杉浦能舞台を尋ねるミニツアーも開催!
●お話―能の歴史と演目の解説
●謡(うたい)に挑戦!
●面(おもて)をつけてみよう!…4名程度体験します
●お囃子っておもしろい!―囃子の解説と小鼓体験
●舞囃子を楽しむ!―『経正(つねまさ)』/シテ:杉浦豊彦
舞囃子とは…演目のクライマックスをシテ一人が面・装束をつけず、紋服・袴のままで地謡と囃子を従えて舞うもの。最も面白い部分だけを演じるため、能のダイジェスト版と言えます。
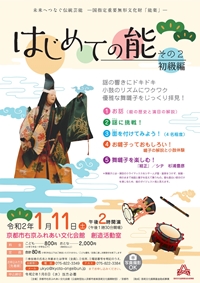 |
 |
★本公演は写真撮影OKです!
ぜひたくさん写真を撮って、お友だちやお知り合いの方にご紹介ください。
SNS等への投稿も大歓迎です!
★前回の『はじめての能 超入門講座』の様子はコチラから!
未来へつなぐ伝統芸能 ―国指定重要無形文化財『能楽』―
はじめての能 その2 初級編
2020年1月11日(土)14:00開演 (13:30開場)
京都市右京ふれあい文化会館 創造活動室
【料金】こども 800円(小学3年〜中学生以下)/おとな 2,000円
※小学生2年生以下入場不可
【定員】合計80名/こども優先
(定員に達し次第受付を終了いたします。)
【お申し込み方法】
★お申込みナシで当日参加もできます。
直接会場(創造活動室)へお越しください。
1. 参加者の氏名と年齢または学年(全員)、2. 住所、3.電話番号を明記のうえ、
会館窓口/電話 075-822-3349/FAX 075-822-3384/
メール ukyo*kyoto-ongeibun.jpまでお申し込みください。
(メールの場合、アドレスの「*」を「@」に変えて入力してください。)
【申込締切】2020年1月8日(水)当方必着
【教えていただく先生方】
 |
 |
|
|
杉浦豊彦 シテ方 観世流 杉浦能舞台主宰 |
松井美樹 シテ方 観世流 |
|
 |
 |
|
|
深野貴彦 シテ方 観世流 |
橋本忠樹 シテ方 観世流 |
|
 |
 |
 |
|
森田保美 笛方 森田流 |
林 大和 小鼓方 幸流 |
石井保彦 大鼓方 石井流宗家 |
能舞台見学ツアーもあります!
右京区鳴滝にある「杉浦能舞台」にお邪魔し、総桧(ひのき)造りの舞台と杉浦豊彦さんのパフォーマンスを拝見しましょう!
 |
日程:令和2年2月8日(土)14:00〜(所要時間:約30分)
場所:杉浦能舞台(嵐電「鳴滝」駅下車 徒歩2分)
京都市右京区鳴滝瑞穂町1
費用:500円
定員:約20名(先着順)
お申込み方法:会館窓口で直接お申し込みいただくか、電話(075-822-3349)でご予約ください。
受付期間=令和元年12月15日(日)〜令和2年1月31日(金)19:00まで
主催:京都市右京ふれあい文化会館(公益財団法人京都市音楽芸術文化財団)
京都市
助成:芸術文化振興基金助成事業

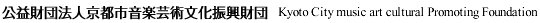
 京都コンサートホール
京都コンサートホール 東部文化会館
東部文化会館 呉竹文化センター
呉竹文化センター 西文化会館ウエスティ
西文化会館ウエスティ 北文化会館
北文化会館 右京ふれあい文化会館
右京ふれあい文化会館 ロームシアター京都
ロームシアター京都 京都市右京ふれあい文化会館
京都市右京ふれあい文化会館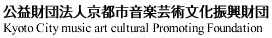
 トピックス/TOPICS
トピックス/TOPICS 施設のご紹介
施設のご紹介 交通アクセス/ACCESS
交通アクセス/ACCESS 自主事業のご案内
自主事業のご案内 パートナーシップ事業
パートナーシップ事業 施設を利用する
施設を利用する 施設の空き情報
施設の空き情報 資料ダウンロード
資料ダウンロード


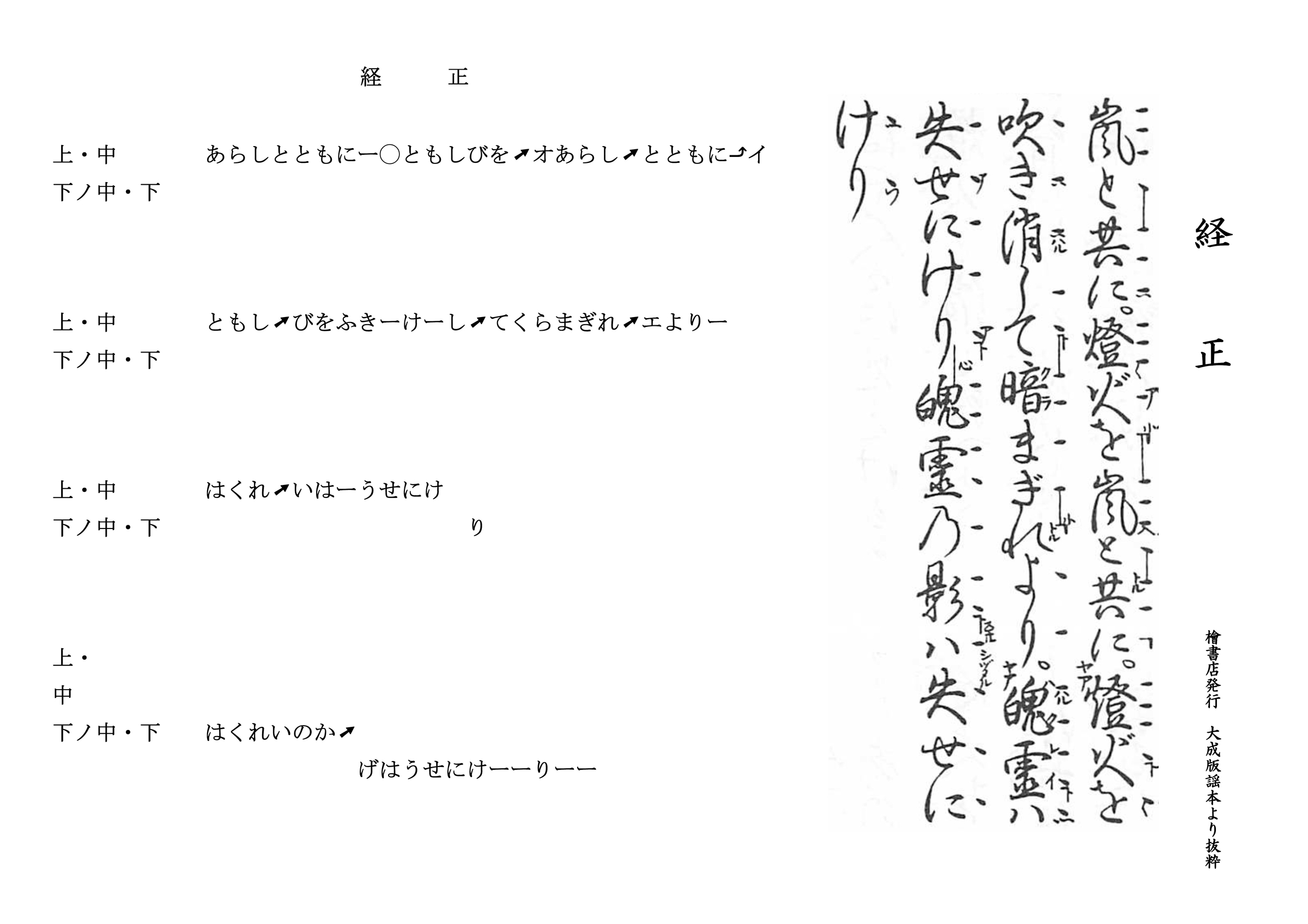
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)